『全部ゆるせたらいいのに』一木けい 著
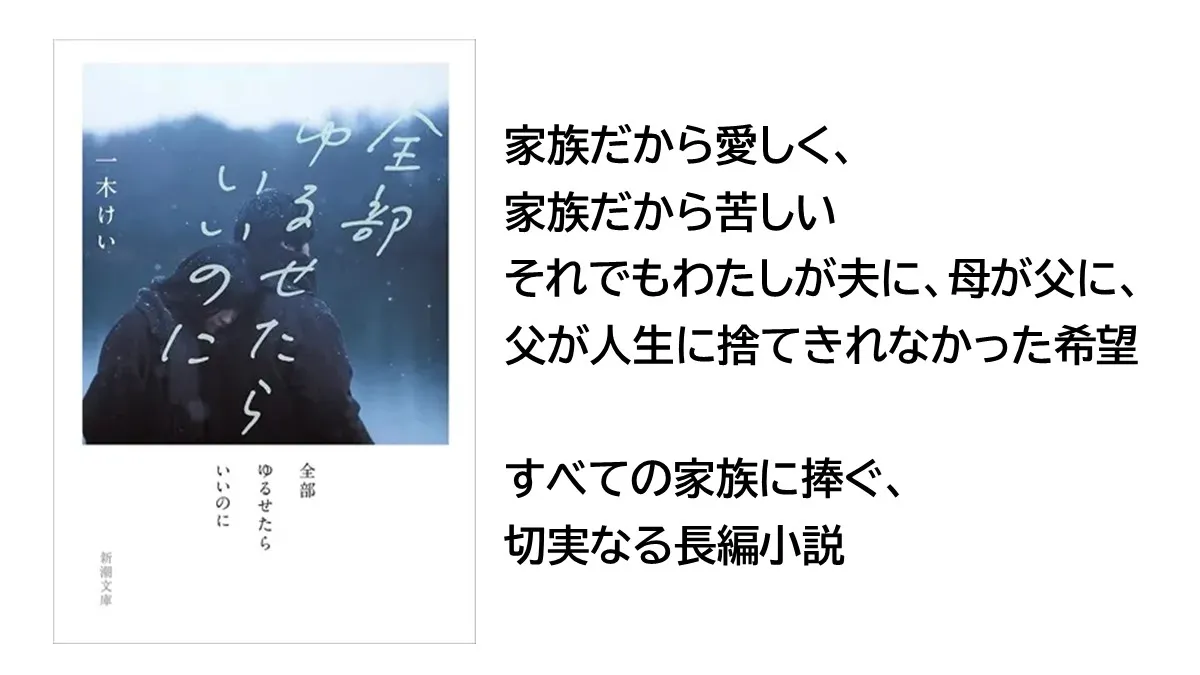
夫は毎晩のように泥酔する。
一歳の娘がいるのに、なぜ育児にも自分の健康にも無頓着でいられるのだろう。
ふと、夫に父の姿が重なり不安で叫びそうになる。
酒に溺れ家庭を壊した父だった。
夫は、わたしたちはまだ、立ち直れるだろうか――。
家族だから愛しく、家族だから苦しい。
それでもわたしが夫に、母が父に、父が人生に捨てきれなかった希望。
すべての家族に捧ぐ、切実なる長編小説。
Contents
感想
本作は、酒に溺れる夫の姿に、かつて酒で家庭を壊した父の姿が重なり、家族とは、家族愛とはについて深く考えさせられる家族小説です。
家族の中でのリアルな心理描写は読みごたえがあります。
家族とは、良くも悪くも切っても切り離せない繋がりであって、その関係性が例えば互いに支え合うものであれば、それはとてつもない固い絆として結ばれます。
しかし、その逆もまたしかりで、その関係性が憎み合うものであったりいがみ合うものであれば、その呪詛もまた強く固いものとなります。
「家族だから」「家族なのに」という言葉が支えになるか呪詛になるか。
それでも離れることも手放すこともできない時、どうすることが正解なのか。
深く愛することの難しさ、報われない想いを受け入れることの難しさ、そして赦すことの難しさ、家族という形の難しさが、ずっしり響く作品でした。
親子の関係をはじめ、家族のありかたに迷いを感じている方、ぜひ一読してみてはいかがでしょうか?
こんな人にオススメ
リアル過ぎる家族小説を読みたい!
家族のあり方に迷っている






